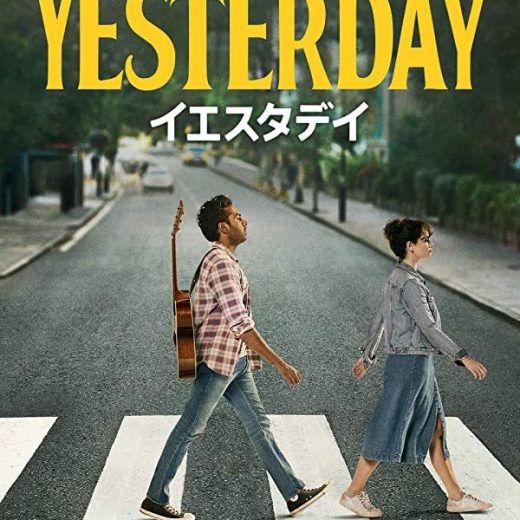こんにちは、元臨床心理士の春井星乃です。
現在は、心理学・精神分析・エニアグラムを通して性格構造を明らかにする「イデアサイコロジー」を提唱しています。
『鬼滅の刃』の記事でいまの若い子のメンヘラ事情について調べていたとき、まきしむから「今若い子の間で心中の曲が流行ってるらしいよ」と聞いたんですよね。
そのときは「えー、心中?」くらいにしか思ってなかったのですが、その後YouTubeで『鬼滅』の考察で100万再生超えの動画をバンバン出してるユーチューバーさんが、『鬼滅』のつぎにその心中の曲の考察をやると言ってたんです。リクエストが非常に多かったからと……
ここで私は「これはもしかして同じ層が反応してる?」と思いました。
その心中の曲とは、プロデューサーayaseとボーカルikuraのユニット、YOASOBIの『夜に駆ける』という曲です。
2019年の7〜9月に、ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する小説・イラスト投稿サイト「monogatary.com」で行なわれていたコンテスト『モノコン2019』において、「ソニーミュージック賞」で大賞に輝いた物語を楽曲化するユニットとして、結成されました。
そして、つい先日、6月1日付けのオリコン週間ランキングでは、『夜に駆ける』が1位を獲得しています。5日には、NHKあさいちにもYOASOBIがリモート生出演していました。
この原作小説を読み『夜に駆ける』を聞いてみると、これはまさに私が『鬼滅』の記事で書いたことと同じものを表現している曲なのではと感じたんです。
それから、私はYouTubeでメイク動画を見るのが好きだったりするんですが、最近「地雷メイク」「地雷女」というワードをよく見かけるようになりました。
「地雷女」とは、簡単に言えばメンヘラの女性という意味です。精神的に不安定で、つきあうとめんどうな女の子ということですが、これが5月に入ってグーグル検索数が急激に伸びているんですよね。
「地雷メイク」とは地雷女がしているメイクで、白い肌、赤っぽいアイシャドー、涙袋、極端なタレ目、赤いリップが特徴になっています。
先日、テレビでも「地雷メイク」が取り上げられて、益若つばささんが「闇っぽいファッションが流行っていて、それに合わせる形で地雷メイクが好まれているのでは」と説明していました。
『鬼滅』の記事では、2000年代初頭で終わった境界例的な文化が違う形で復活してきている、心の闇に若者の関心が向かいつつあるということを書きましたが、それが今、さらに大きな流れになって生じつつあるのではないかと思いました。
この記事では、『夜に駆ける』の紹介とその背景の音楽事情、『鬼滅の刃』との共通点、90年代との比較などを通して、この流れが実際はなにを意味するのかを考えてみたいと思います。
メンヘラをニュートラルな曲と声で表現する手法
巧妙に「自己を消す」YOASOBI
ポストモダンと生と死の意味
死への憧れは「自己を消す」が行き着いた究極のもの
他者の時代を生きるためには「死」の知識が重要
『タナトスの誘惑』と『夜に駆ける』の紹介
それではまず、原作小説『タナトスの誘惑』を読んでみましょう。すごく短く簡単な文章なので、すぐ読めると思います。
monogatary.com
タナトスとは、小説中にも説明がありましたが、正確にはこのブログでもしょっちゅう出てくる心理学者フロイトの専門用語で、死の欲動という意味ですね。
一般的には、タナトスは無意識的な自己破壊的・自己処罰的な衝動と理解されます。治療中に、患者さんが治癒に抵抗したり、症状を悪化させたりするときにタナトスが働いていると解釈されたりしますが、この小説では単に「死にたいという衝動」として描かれています。
この作品のストーリーは、主人公の僕が自殺しようとしている女性に出会って一目惚れし、何度も彼女の自殺を止めますが彼女は一向に僕を受け入れてくれない。でも、ある日、彼女がまた「死にたい」と言ったときに、思わず「僕も死にたいよ」と言うと、そこで彼女がはじめて笑顔になって「やっと気づいてくれた?」と言う。そして、2人は共に『夜に駆ける』……というものでした。
では、これを踏まえて『夜に駆ける』を聞いてみましょう。
メンヘラをニュートラルな曲と声で表現する手法
さて、みなさん『夜に駆ける』どう感じましたか?
まず、楽曲の方からみていきますね。
プロデューサーのayaseさんは、2018年12月からボーカロイド(音声合成技術)の初音ミクを用いた楽曲をニコニコ動画とYouTubeに投稿し、活動を始めたボカロP(ボーカロイドプロデューサー)。
なので、この『夜に駆ける』にもボカロ文化から引き継がれた要素が見られます。
特徴的なのは、間奏やメロディーの裏で流れる細かく早い動きのピアノ&電子音。これは、ボカロ文化の特徴的な音作りで、近未来的な、感情を排除したニュートラルな雰囲気を作り出します。
そして、ayaseさんの作り出すキャッチーなメロディも相まって、曲だけ聞くと心中の曲とはまったく分からない、オシャレでノリの良い曲になっているんです。
そして、ボーカルのikuraさんの声も非常にニュートラルで、ボーカロイドに極力近づけたような歌い方をしているように感じます。
また、歌詞も一見しただけでは心中の歌詞とは分からない内容になっています。原作小説を読んで、改めて見たときに「あー、これはこのことを言ってるんだ」と分かるという作りになっているんですよね。
それなのに、その奥には、「心を病んだ彼女を助けようとするが、彼女が望んでいたのは死で、結局2人は死に希望を見出して共に死んでいく」という非常に重い内容が隠されているんです。
この彼女はメンヘラの定義のうちに入ると思うのですが、このメンヘラ的な内容を、オシャレでニュートラルな曲と声によって表現するというのが、『夜に駆ける』のヒットの大きな要素の1つなのではないでしょうか。
『鬼滅の刃』でも、境界例的・メンヘラ的な「死への恐怖」「見捨てられ不安」「絆を確認するために周囲を操作する」「疎外感」などの闇要素を「鬼」を通して描くこと、そして主人公を「いい子」にすることでオブラートに包んで表現していました(『鬼滅の刃』大ヒットの本当の理由とは?新ジャンル「役に立つメンヘラ」説)。
つまり、2000年代初頭以降の、他者軸で動くことがよいとされ感情を表現することが嫌われる「他者の時代」においてメンヘラ的なものを表現するために、直接的ではなくオブラートに包んだ形で出すという手法が『鬼滅の刃』でも、この『夜に駆ける』でも使用されているということです。
『鬼滅』の記事でも書きましたが、やはり、いま、2000年代から抑圧されてきた心の闇への関心が急激に高まっているように思います。
でも、それを90年代のようには出せないので、表面的には感情を排除したニュートラルでオシャレな曲でカバーして表現するという技法が生まれたのではないかと思うんですよね。
巧妙に「自己を消す」YOASOBI
また、他者の時代の特徴として、自己の存在感をできうる限り消すことが好まれるというものがあります。自己の感情やキャラが強いのは嫌われます。『鬼滅』の主人公炭治郎も自分の感情をめったに出さず、常に他者目線で動くいい子でした。
でも、たとえば、90年代から2000年代初頭のメンヘラ的なアーティストとしては、浜崎あゆみとか椎名林檎、鬼束ちひろなどがいますが、彼女たちはすべて自分の個性や感情を前面に出して、それをウリにしていましたよね。曲も非常に感情に直接訴えかけるものになっています。
それに対して、最近のYOASOBIも含むメンヘラ的な内容を歌詞にしているアーティストのミュージックビデオは、ほとんどがアニメなんです。自分が歌っている姿を出さない。
そして、YOASOBIはその究極の姿だと言えると思うんです。他人が書いた小説をもとに曲を作ることで、メンヘラ的なものはYOASOBIにあるわけではないということになり、YOASOBIの2人のキャラが確定しないんです。
そこに、ボカロ文化の感情を排除したニュートラルな曲づくりと声が合わさり、2人のキャラは無味無臭で空気みたいなものとなります。すると、聞いた人が同一化や感情移入しやすくなるんですね。
また、曲で感情を表せない分、聞いた人が感情移入がしにくいので、逆にその奥にある物語を必要とするという面もあると思います。
音で直接感情を揺さぶるのは刺激が強いので、感情部分は別メディアの文章表現でワンクッション置くという手法を取るんですね。ホントによく考えられています。
ポストモダンと生と死の意味
そして、もうひとつ、『夜に駆ける』の意味を考えるとき重要になってくるのが「死」の捉え方です。
『夜を駆ける』には、現実と自分に対する深い絶望と、死だけがそこから解放してくれるんだという考え方がありますよね。
私は2019年の4月に、ナゾロジーで「反出生主義」についての記事を書きました。反出生主義とは「人間は繁殖するべきではない」という哲学的な立場なのですが、その記事で「反出生主義」が生まれた思想的土壌、ポストモダンについて以下のように書いています。
星乃:反出生主義というのは、人生に希望が全く持てないということから来ているように思うんだけれど、今の時代がまさに、人生に希望が全く持てない、人生の価値が全く見えない時代なんですよね。これは70年代からのポストモダンの影響が大きいんじゃないかな。
――希望が持てないというのもありますし、昔と違って「こう生きるのがベスト」みたいな規範や価値が相対化されているのもありますよね。ここにポストモダンがどう影響してくるのでしょうか?
星乃:モダンとは近代という意味なので、ポストモダンとは近代以降という意味です。近代というのは、科学が発達してきた産業革命以降から第二次世界大戦くらいまでを指すのだけど、そのくらいのときって、人類は科学によって豊かで皆が幸せに暮らせる時代がやってくるという期待を持っていたんです。
でも、そんなことには全くなってこなかったでしょ。だから、社会や人類全体がどうかという大きな視点を持つことに興味を持てなくなっていった。
そして、同時に思想界では、そもそも人間には主体性なんてなくて、ただ無意識のシステムに動かされているだけの存在とする考え方が出てきたのね。そうなると、価値観なんて人それぞれでいいってことになって、人類共通の真実や価値なんて存在しないという考えが主流になったんです。これがポストモダンの相対主義ってやつです。
――なるほど。そもそも今の時代は「絶対的な人生の価値なんてない」ってことになっているんですね。
星乃:そうなんです。そして、人間は無意識のシステムに動かされているだけの存在なんだから、当然「成長」というのも幻想にすぎない。人生に価値を見出すのも個人が勝手にやってるだけで、本当は意味がないかもしれない。
脳科学からしたら、人間の意識でさえただのシナプスの化学反応に過ぎないかもしれないわけです。そんな考えが、特に今のアカデミズムでは主流になっているんですから、社会の風潮もそれに影響を受けて、「生きていることなんて意味がない」ということになっていきますよね。
しかも、現在は格差社会で、貧富の差がどんどん開いていっています。生活に余裕のない人が増えていますし、努力しても一発逆転なんて夢のまた夢という状況です。それでは、人生に希望なんか持てるわけないですよね。
ナゾロジー:2019年4月9日「なぜ生んだ?反出生主義者の「深層心理」を心理学的に分析してみた」
このように、いま、アカデミズムでも一般的な社会的風潮としても、「生きる意味なんて分からない」というのがメジャーな考え方になっています。
個人個人が自分で意味を見出さなければならないんですよね。でもそれって、よほどの時間と労力をかけて、知識を得て思考を重ねていかなければ得られないものなんです。日本では特に、自己責任とすぐ言われますしね。
こんな状況では、生きる意味を見いだせない若者が出てくるのも当然なんです。
そして、その流れでここ数年「安楽死」も話題になることが増えました。
2016年には脚本家の橋田壽賀子さんが安楽死に関する本、作家の沖方丁さんも『12人の死にたい子どもたち』という作品を出版しています。

▲amazon.co.jp 沖方丁『12人の死にたい子どもたち』
2018年には社会学者の古市憲寿さんが安楽死をテーマにした小説を書いています。2019年には、『12人の死にたい子どもたち』が映画化、オーストラリアの安楽死合法化で日本でも安楽死が大きな話題になりました。
反出生主義も2013年ころからグーグル検索数が急増し、2019年にはインド人の青年が両親を「勝手に産んだ」と訴えたというニュースがネットで話題になりました。
「死への憧れ」は「自己を消す」が行き着いた究極のもの
そして、今回の『夜に駆ける』のヒットにつながるわけです。
この「死への憧れ」は、先程お話した他者の時代の「自己の存在をできうる限り消す」の行き着いた究極のものなんじゃないかと私は思うんです。それがカッコいいものとして認識されつつある。
90年代の自己の時代の境界例的・メンヘラ的な文化は、リストカットやオーバードーズ(大量服薬)、死体写真など刺激の強いものを自分の個性として使った自己表現でした。「死」に興味はありましたが、それはあくまで自分主体で、生を意味のあるものにするための手段だったんですね。
でも、今回の『夜に駆ける』は、絶望と純粋な「死への憧れ」であり、「死だけが自分を救ってくれる」というメッセージになっているんです。究極に自分を消し去ることがカッコいいということですよね。
そこまで今の若者は追い詰められている……だからこそ、2000年代から抑圧してきた心の闇に向き合わざるを得なくなってきたということなのかもしれません。
でも、それを直接出すと否定や批判されるのが怖いので、巧妙にオブラートに包んで表現して、なんとか溜まったものを処理しようとしている。
地雷女・地雷メイクも、自ら「地雷女」ということで、「自覚しているだけマシと思われる」「地雷女という演技をしているだけで本当は違うと思われる」「もしメンヘラ的な行動をしてしまっても許される」というメリットがあるみたいなんですね。
つまり、地雷女・地雷メイクも、心の闇を否定されないようにオブラートに包んで出すための手段なのかなと私は思っています。
他者の時代を生きるためには「死」の知識が重要
でも、本当に「死」って、『夜に駆ける』で描かれているような「全ての苦痛から救ってくれる救世主」みたいなものなんでしょうか。
『夜に駆ける』の彼女は、純粋に死にしか興味がないように描かれていますが、現実では、どんなに境界例的な症状が重くても、みんな本当は「生きたい」んです。私の患者さんを見ても、みんなそうです。
これは、自己の時代、他者の時代で変わるものではなく、人間であればそうだと私は考えています。
ただ「生きるのが死ぬより辛い」「死んでこの辛さから解放されたい」と思うから、「死にたい」と言っているだけなんです。周囲にもそれを理解する人がいないから。
そして、「死」についての知識がないからというのもあります。古今東西の哲学・思想史・心理学・歴史には、本当は、世界とは、人間とは、意識とは、生きるとは、死とはということに言及しているものは沢山あります。
主人公の僕は、死ぬ気であるならば、必死で勉強して自己研鑽を積み、本当に彼女を理解して生に導くことができていれば、そっちのほうが本当の「救世主」だと私は思うんですよね。
ただ、自分なりに「死」についての見解を持つには、複数の分野におけるかなりの量の知識が必要になります。
この「死」について、哲学・思想史・心理学・精神分析・歴史・量子論などの幅広い分野から語っているのが、2019年に出版した『奥行きの子供たち』です。

「死」とは一体何なのか、この先人類はどうなっていくのか……など、対談形式で分かりやすく述べています。
もしよかったら、ぜひ読んでみてくださいね。
他者の時代の「自己の存在を消そうとする風潮」に打ち勝って幸せに生きるために、このような知識はとても重要だと私は思っています。